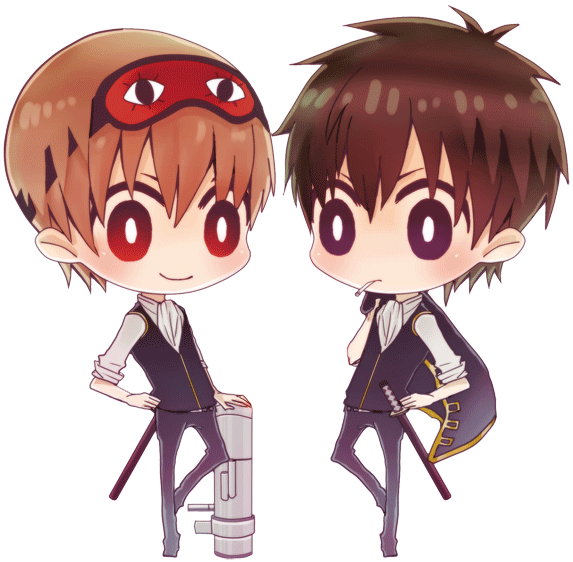「おはよう」なんて、今まで散々言って来た言葉がこんなにも愛おしくて。
アンタの隣で目覚める朝は、こんなにもしあわせで。
この気持ちを、どうしたらアンタに全部伝えられるだろう。
*****
「というわけで、これどうぞ」
「どういうわけだよ…」
俺が差し出したそれを、それはそれは嫌そうな顔で見下ろしながら土方さんが溜息まじりに零す。
受け取ろうと手を出す素振りも無いとはなかなかに愛の伝わらない人だと、俺も眉間に皺を寄せて深い溜息を吐いた。
「いや、なんでお前が溜息吐くわけ…そもそも何の嫌がらせだこんなもん」
「そろそろアンタの誕生日だった気がしたんで、愛を込めてプレゼントでさァ。少しは嬉しそうな顔とか出来ねェんですかサイテーだな、オイ」
「出来るかァァァァ!!だいたい誕生日一ヶ月以上先ですけど!しかもなんだこの目に痛いピンク!!なんだこのYESって!見覚え有るけど認めたくねーよお前がそこまでバカだったとは認めたくねーよ!!!」
「ああ、なんだ。知ってんなら話は早ェや。んじゃ、早速今晩から使ってくだせェ」
ショッキングピンクのサテン地にでかでかとプリントされた「YES」の白文字。同素材の大きなフリルが縁取りするそれは新婚さんがいらっしゃるあの番組でおなじみの夜のコミュニケーションツールだ。
しかも特別仕様。見つけるのに苦労したが、怒鳴り散らした土方さんの耳のあたりが赤くなっていたのを俺は見逃さなかった。喜んでもらえて何よりだ。
「じゃ、俺は道場に行かなきゃならねェんで、今夜楽しみにしてやす。晩飯は犬のエサ以外でお願いしまさァ」
立ち尽くす土方さんに夕飯のリクエストをして玄関に走る。土日休みの公務員と違って、道場は土日こそ出稽古だの練習試合だのと忙しいのだ。
そのせいもあって、丸一日ゆっくり一緒に過ごすなどという事は滅多に無いし、いつもどちらかが疲れている。だからというわけでは無いが、色っぽい事がまるで起こらない。
しかし、めでたく七年越しの片想いを成就させたあの雨の日から今か今かと事に及ぶタイミングを計っていたのは俺だけでは無いはずだ。多分。きっと。
計っていなかったとしても、土方さんだって俺の気持ちを受け入れてこうして同居を続けているのだから、それなりの覚悟はあるという事だろう。
かといって、僅かな期待を抱いていたとしても、それを自ら言い出すような人ではない。俺が踏み込めば良いのだろうが、「今夜どうですか」などと言い出してにべもなく断られてはガラスのハートが粉々に砕けてしまう。つまり、実はビビっているのだ、認めたくは無いが。
恋人と呼べる関係になって暫く経つというのに、俺は未だに朝目覚めるたびにシーツに残るあの人のぬくもりを探して確かめては、ほっと息を吐く。
実は全てが夢で、目が覚めたら俺はひとりなんじゃないだろうか、なんてくだらない不安がいつまでも消え去ってくれないのだ。あんなにも欲して、あんなにも焦がれて、あんなにも無様に求めたくせに、いざ手に入ってみたら今度は自分でも理解し難い不安に怯えている。
「情けねェ…」
だから、さっさとあの人を抱いてしまいたいのだ。それが恋人同士の全てじゃない事はもちろん承知しているけれど、あの人の全部を見て、あの人の奥まで触れて、その体温を直に確かめたい。夢じゃない、現実のものだと、確かに感じたいから。
しかし誘う勇気も無い。そこで考え付いたのが件の枕だった。我ながら素晴らしいアイディアだ。
近藤さんの道場へ向かうため故郷への電車に揺られながら、段々と長閑になって行く景色を眺めて今宵に想いを馳せたら思わず不気味な笑い声が漏れて、人影もまばらなローカル電車の乗客達が怯えた表情で目を逸らす。だけどそんな事は、少しも気にならなかった。
*****
アパートの外階段を駆け上がる足取りが軽い。わざわざ途中下車してまで寄った激安の殿堂のレジ袋には、今晩のそれに必要だと思われるあれやこれやが紙袋に隠されて入っている。
「ただいまー」
勢い良く開けた玄関まで漂う夕飯の匂いに腹がぐうと鳴ったが、それどころでは無い。
「おう、おかえり」
リビングから聞こえた愛しい声も素通りして寝室のドアを開ける。視界にちらりと映ったドピンクは紛れも無く俺がプレゼントしたあの枕だった。
急に心拍数が上がる。飛び上がるほど嬉しいとはこの事か。ガサガサと鳴るレジ袋を揺らして、小さくガッツポーズを決めたのは無意識だった。
あの枕が俺の方にあるのは素直じゃない土方さんの照れ隠しだろう。あんなケバケバしい色の枕で眠れる気がしないので、事が済んだら丁重にお返ししよう。
今夜ついに積年の願いが叶うのだと思うと大声で笑いたくなるけれど、そんな事でどん引きされて台無しになっては困るのでぐっと堪える。
ベッドヘッドに明るい家族計画とぬめっとしたアレを忍ばせるべく近付いて、そこで初めて枕の異変に気付いた。
俺がプレゼントしたのは、表に「YES」裏にも「YES」とプリントされた枕であって、つまり「NO」は無いはずなのに。
そこにあったのは、白いビニールテープで大きくバツ印を付けられたイエスノー枕…もとい、イエスイエス枕だったのだ。そんな意思表示があったとは盲点だった。
「…ッ!あの野郎……」
すぐさまそれを引っ掴んでリビングへ引き返す。
「アンタこれ、何してくれてんでィ。俺の愛を何だと思って……」
「何してくれてんのはこっちのセリフだボケ!俺の意思丸っと無視してんじゃねーか。どんだけドS仕様だよ」
「ちッ…バレたか……」
「バレバレだろ、隠す気ねぇじゃねーか!」
おそらく土方さんがちまちま貼り付けたのだろうビニールテープを爪で剥がしながら、つまんねぇの、と呟くと土方さんがまた溜息を吐いた。
この人は一日に何度溜息を吐くのだろう。今度数えてみようと思う。
「ったく、くだらねぇ事考えるよな。ほら、さっさと食っちまえ。片付かねぇから」
「母ちゃんか」
「何でも良いから食えっつってんだろ!」
「へいへい。いただきまーす」
並べられたのは見栄えも何もあったものではない、いつもながらの豪快な炒め物だった。しかしながら、味はなかなかに良いのでマヨネーズさえかけてくれなければ何も不満は無い。
白いビニールテープを手のひらで丸めてゴミ箱にシュートして、枕を床に放ってしまおうと思ったけど片付けろと怒られそうなので抱えたまま食卓についた。
「おい、総悟マヨネーズ」
「へい、母ちゃん」
「誰が母ちゃんだ」
サラダにほんの少し使ったマヨネーズを渡すと、土方さんは料理の姿が見えなくなるまでにょろにょろと絞った。それはもう子供の頃から毎日のように見てきた光景なので特に驚きも嫌悪もしないけれど、流石に白飯にまでたっぷりかけるのはどうかと思う。
それでも、決して美味そうには見えないその物体を一気に掻き込む土方さんを見て、ざく切りにされた歪な野菜を頬張るこんな毎日は、多分誰にも想像がつかないくらいに楽しいのだ。どうしようもなく頬が緩む。
「土方さん」
「あ?」
「これ、使います?」
やっぱり愛しくて仕方がないのだと再確認して、食欲も満たされたら次は違う欲を満たしたくなった。あれこれ言い訳してみても、男なのだから仕方がない。土方さんだってきっと同じ。
それなのに、元の姿に戻ったイエスイエス枕を差し出したら、目の前で飯を平らげたばかりの恋人はいつもの二倍の皺を眉間に刻んで無言で立ち上がった。そのまま空になった食器を持ってキッチンに消えてしまう。
男相手に抱き合いたいと思う俺が異常なのだろうか。キスを拒みはしないくせに、その先には抵抗があるなんて言うつもりならこれは話し合う必要がある。今後のためにも。
「ひじ……」
呼びかけて、そういえばキスだっていつも俺からだと気づいた。土方さんは拒まないだけで、望んでいる訳ではないのかもしれない。
「そうかよ…俺が異常なんだろィ……ちくしょーむかつく…」
「なにブツブツ言ってんだ、片付けろ」
「俺ァいま悟りを開けそうなところまで来てるんでィ、邪魔すんな土方」
テーブルに上半身突っ伏した俺の頭を手加減無しにぶん殴るくせに、食器は片付けてくれる。この人は母ちゃんだ。母ちゃんだと思えばあんなことやこんなことなど想像できなくなるはずだ。
「……ンなわけねェか」
全く何の役にも立たない対策を思いついては打ち消して、また溜息を吐く。土方さんは洗い物を終えて寝室に行ってしまった。きっと着替えを取りに行って風呂に入るのだろう。いっそ風呂に乱入してやろうか。そんなことよりも、枕元にあれやこれやを置きっぱなしだった。あの人が紙袋を開けなければいいのだけれど。
ゴトン、と何かが落下した音が聞こえたということは、神様が俺の願いを無視したということか。
「あーあ…うまくいかねェなァ……」
伸びをしたら抱えていた枕が落ちたので蹴飛ばしておいた。多少ふざけていたことは認めないでも無いけれど、茶化しでもしなければ踏み出せなかったのに。この状況で床に転がるそれは、あまりにも馬鹿げていてイラっとする。
拾うのも嫌で、定位置に移動してテレビを付けた。
「総悟、先に風呂使う……って、近ェって言ってんだろ!目悪くすんぞ」
「あー、どうぞお先に。俺の事はお気になさらず」
「テメェは…まだ拗ねてんのか、ガキ」
「何の話ですかね、ちょっとわかりやせん。今忙しいんで話しかけないでもらえますか」
相撲中継から目を離さずに応えていたら、背後から深い溜息が聞こえた。いつの間にかすぐそばまで来ていたらしい。
「総悟、」
「なんでィ」
それでも振り向かない俺に小さく舌打ちして土方さんが、風呂行ってくるわと立ち去った直後。
ぼふん。
「………ッ!」
俺の後頭部めがけて飛んできたのは、食卓の下に転がってる筈の、ドピンクの、新婚さんがいらっしゃる番組でおなじみの、夜のコミュニケーションツール。
そして、我が家のそれには「NO」が無い。
ほんの少し、また距離を縮めた俺達は、明日どんな顔で「おはよう」を言うのだろう。
「ともる、走馬灯の夢」後日談(byゆき乃)です。
先に進むのにいちいちめんどくさい二人だったら可愛いなと思ったらこんな感じになりました。
本編あんなにシリアスだったのに、下ネタに走ってすみません……後悔はしていなi…ry
読んでいただいてありがとうございました!
先に進むのにいちいちめんどくさい二人だったら可愛いなと思ったらこんな感じになりました。
本編あんなにシリアスだったのに、下ネタに走ってすみません……後悔はしていなi…ry
読んでいただいてありがとうございました!